『教養としての神道―生きのびる神々』を読みました。
著者は島薗進さん、発売は2022年、東洋経済新報社から。
内容/あらすじとか
明治以降の近代化で、「国家総動員」の精神的装置となった「神道」。近年、「右傾化」とも言われる流れの中で、「日本会議」に象徴されるような「国家」の装置として「神道」を取り戻そうとする勢力も生まれている。
では、そもそも神道とは何か。
神道は古来より天皇とともにあった。神道は古代におけるその成り立ちより「宗教性」と「国家」を伴い、中心に「天皇」の存在を考えずには語れない。
しかし「神道」および日本の宗教は、その誕生以降「神仏習合」の長い歴史も持っている。いわば土着的なもの、アニミズム的なものに拡張していった。そのうえで神祇信仰が有力だった中世から、近世になると神道が自立していく傾向が目立ち、明治維新期、ついに神道はそのあり方を大きく変えていく。「国家神道」が古代律令制以来、社会にふたたび登場する。神聖天皇崇敬のシステムを社会に埋め込み、戦争へ向かっていく。
近代日本社会の精神文化形成に「神道」がいかに関わったか、現代に連なるテーマをその源流から仔細に論じる。同時に、「国家」と直接結びついた明治以降の「神道」は「異形の形態」であったことを、宗教学の権威で、神道研究の第一人者が明らかにする。(Amazonより)
『教養としての神道 生きのびる神々』の感想/レビュー
カジュアルな印象のタイトルに反して、難しい内容の神道入門書でした。特定の宗派や思想に偏らず、客観的に神道史を俯瞰しているので全体の流れを掴むのには最適だと思いました。
神道についての大きな疑問として本書が追っていくのは、「日本の古代信仰がなぜ生き残れたのか、そしてどのように生き残ってきたのか」ということ。その答えの一つとして日本が律令国家体制になった時、国の宗教として現代の神道の基礎となるような仕組みが整えられたことが挙げられます。
またそうした動きのなかでも、地方ごとに根付いていた信仰も尊重されていたため(支配が行き届かなかった&各地の信仰も強大で無視できなかった)、それらは国家神道とは別に独自の発展を遂げていきました。
仏教や儒教の影響を受けて変化しながらも、それらの影響から自立しようという動きはたびたび起こっています。その都度「神道とは何か?」を問い直してきたことが、神道を生き残らせてきたのではないかと解釈しました。
以下、ざっくり自分なりに神道史まとめ。
- 律令国家の神道(7〜8世紀頃):国家的な祭祀、崇敬の対象としてアマテラスを祀った伊勢神宮が成立。宮廷祭祀を行う神祇官という組織を設置。国家の起源と皇室の歴史を記した古事記・日本書紀を作成。神祇官は早い段階で頓挫、代わりに二十二社一宮制(位の高い神社を22社に絞って国が捧げ物をした)を導入、朝廷の負担を減らした。そのため地方の神社にまでは朝廷の拘束力が及ぶことはなかった。神祇官は白川家、吉田家に掌握され、皇室と距離が出来ていった。
- 中世の神道(11〜15世紀頃):仏教や儒教の価値観が混ざり古事記は多様に伝承・解釈され「中世神話」となった。律令国家神道は存在していたものの、影響力は弱かった。南朝の家臣だった北畠親房が、「万世一系で天皇が続いている日本は優れた国である」という国体論的な考え方を示した。天皇による支配の正当性を強調。
- 安土桃山から江戸の神道(16〜17世紀頃):仏教と儒教の影響を受けた吉田神道の誕生。国家祭祀が再び勢いを取り戻す。仏教と大名の衝突、キリシタンとの関係を経て、家康は国家的な宗教の必要性に迫られる。自身を祀った東照宮を創設(信長や秀吉も自身を神にしようとする動きがあった)。応仁の乱以後あいまいになっていた宮廷祭祀の整備と再興。儒学の振興と正統的統治の理念化。
- 幕末から明治の神道(19〜20世紀頃):尊皇攘夷論と国体論による、天皇中心の神道思想が生まれる。神仏分離により、古代の律令国家神道を再興させようとしていたが、大きく異なっていたのは神聖天皇崇敬という、過剰なまでに尊王的な側面を押し出していた点。新たな国家神道を広く国民に浸透させたのに、学校教育(教育勅語)、軍隊、祝日の設置、治安維持法などの影響が大きかった。明治以降に創建された神社には、天皇制国家のために殉職した人、南北朝時代の南朝方の忠臣(楠木正成など)、天皇や皇族を祀ったものが大半だった。
『教養としての神道 生きのびる神々』のハイライト/印象に残った箇所
大和朝廷はアマテラスを高い地位に置いたが、各地の信仰の力も容認した
7世紀は国家祭祀ができて伊勢神宮の存在が定められていく時代だ。律令制度の下で国家財政で支出する神社ができる。その一方で仏教と組んで託宣を下すなど、民衆の信仰を集める神仏習合的な信仰が広まっていく。そのうち八幡信仰は大仏の建立を助けたことから、国家的な影響を持つようになった(島薗 2022:114)
大神神社、宇佐八幡宮、伏見稲荷大社などは、大和朝廷が支配を固めていく時期にはすでに、大きな力を持っていたようです。もちろん勢力は小さくとも、各地にもそれぞれの豪族に祀られている信仰がありました。それらをないがしろにしなかったことが、神道が生き延びる基盤となっていったのです。
日本の律令体制では、神聖王権を支える国家儀礼は朝廷と伊勢神宮で行われるアマテラスの祭祀だ。だが、その祭祀が及ぶ範囲は限られていて、各地域では地域の神祇祭祀が力をもっていることが容認されている。(中略)大和朝廷の神々の体系は統合されているようで分散しており、そのような形態を取ることで、朝廷の神祇信仰も各地の神祇信仰もそれぞれに力を維持して長い歴史を経過し、現代に至ったということを示していきたい(島薗 2022:119)
明治以降の国家神道の基礎は、15世紀頃にあった
律令国家神道は存続したものの、中世においては統合性という点でも影響力という点でも後退局面にあったといわざるをえない。その間に、近代の国家神道に連なるような神道の基盤を培ったものとして、本書では北畠親房と、吉田兼倶に注目した。この両者は国家機構や政権からは距離のあるところで、独自の神道的観念や神道的組織・実践を形づくっていったものであり、律令国家神道の展開とはいいがたいものである(島薗 2022:267)
明治以降に興隆した国家神道の大きな特徴は、天皇崇拝の側面が強かったということです。日本が王朝の交代などをせず、天皇が続いてきたことから優れているという国体論。この元となる考え方は、南朝の北畠親房が後醍醐天皇をバックアップするため、天皇が国を統治すべきという根拠と正当性を強調するために打ち出されました(『神皇正統記』を執筆)。
吉田兼倶は15世紀末頃に仏教と儒教の影響を受けながら、「吉田神道」という教派を作りました。その特徴は教義や経典を持ち、仏教からの独立を意識していたことです。吉田神道はその後、400年近く神道界で巨大な力を持ち続けます。
有名な神社への参拝者数は増加傾向にある
1970年頃から2020年頃までの神社参拝者数の推移からは、親族や地域集団の結合による宗教行動が後退し、代わって分散した個々人や家族による宗教行動が増大しているという傾向の現れとみてとれる。帰属する対象としての宗教集団からは離れていくが、自由に接近できる宗教資源には進んで接近する傾向が強まっているので、大きな神社には人が集まりやすくなっているということだろう(島薗 2022:340)
神社本庁による調査では、地域の氏神を知っているか、氏神のお札を持っているかについて、1996年から2006年までにどちらもおよそ10%ほど低下しているそうです。ただ著名な神社への初詣者数は増加傾向にあり、これは観光の振興と関わりがあると考えられているようです。






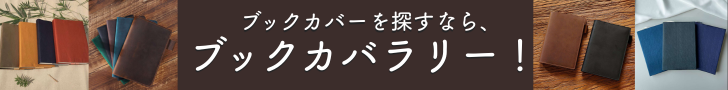



コメント