今回はレイチェル・カーソンの『センス・オブ・ワンダー』を読みました。
訳は上達恵子さんで、2021年に新潮社から出ている文庫版。
元の本はアメリカで1965年に出版されています。
雨のそぼ降る森、嵐の去ったあとの海辺、晴れた夜の岬。そこは鳥や虫や植物が歓喜の声をあげ、生命なきものさえ生を祝福し、子どもたちへの大切な贈り物を用意して待っている場所……。未知なる神秘に目をみはる感性を取り戻し、発見の喜びに浸ろう。環境保護に先鞭をつけた女性生物学者が遺した世界的ベストセラー。川内倫子の美しい写真と新たに寄稿された豪華な解説エッセイとともに贈る。
レイチェル・カーソン(2021)『センス・オブ・ワンダー』(上達恵子 訳) 裏表紙 新潮社
『センス・オブ・ワンダー』で印象に残った箇所
『センス・オブ・ワンダー』で印象に残った箇所は3つあります。
- 圧倒的な自然描写
- センス・オブ・ワンダーは神秘さや不思議さに目をみはる感性
- 解説が面白い
①圧倒的な自然描写
夜ふけに、明かりを消したまっ暗な居間の大きな見晴らし窓から、ロジャーといっしょに満月が沈んでいくのをながめたこともありました。
月はゆっくりと湾のむこうにかたむいてゆき、海はいちめん銀色の炎に包まれました。その炎が、海岸の岩に埋まっている雲母のかけらを照らすと、無数のダイヤモンドをちりばめたような光景があらわれました(上達 2021: 22)
本書は筆者のレイチェルが、甥(正確には姪の息子)のロジャーを連れて海辺や森を探検し、動植物や星空を眺めた経験をもとに書かれた本。
たんなる自然讃歌にとどまらず、誰もが子ども時代に持っていた自然の美しさや神秘を感じる感性を取り戻すこと、その感性を大切にすることを提案しています。
レイチェルとロジャーは昼夜天候を問わず、自然のなかに出かけます。そこで目にした景色は、詩のような叙情的な言葉で描写されています。レイチェルの文章は確かな手応えをもって、読み手の中に眠っている感覚を刺激してきます。
②センス・オブ・ワンダーは神秘さや不思議さに目をみはる感性
子どもたちの世界は、いつも生き生きとして新鮮で美しく、驚きと感激にみちあふれています。残念なことに、わたしたちの多くは大人になるまえに澄みきった洞察力や、美しいもの、畏敬すべきものへの直観力をにぶらせ、あるときはまったく失ってしまいます(上達 2021: 33)
センス・オブ・ワンダーは神秘さや不思議さに目をみはる感性のこと。
レイチェルは誰もが子ども時代には持っているけど大人になる前に鈍らせ、ついには失ってしまうと述べます。感性は数値化できませんが、年を重ね荒んだ日々を送っていると露骨に鈍ってくる感じがします。それを取り戻す術が、本書のなかに散りばめられています。
③解説が面白い
知識の花は感性と霊性を土壌にしたとき、より豊かに美しく開花する。だが、どんなに多くの知識を身に付けても、感性や霊性は動かない。そればかりか、知性や理性すら花開くことはない(上達 2021: 112)
『センス・オブ・ワンダー』はレイチェルの死により絶筆となっているため、70ページ程度と短い内容になっています。そのため、後の半分くらいは四人の作家や教授の解説エッセイが載っています。これらのエッセイがなかなかに読み応えがあるので、本文と合わせて楽しむことができます。
『センス・オブ・ワンダー』の感想
五感で感じる刺激には、謎がつきまとっています。たとえば雨が降る森の中を歩けば、いろんな何かが混じった匂いを感じられます。漠然と「濃い緑の匂いがする」という感想に始まり、そこから生まれた問いに向かって想像力がフル回転します。
あらゆる創作は、そんな風にセンス・オブ・ワンダーを駆使するところから始まるのではないかとお思います。そうでなければ、星々の間に線を引いて人や動物を描くことも、森の中に精霊や神を住ませることもできないでしょう。
最初から説明されていたり答えが分かっている「わかりやすさ」は、それで完結してしまうために想像力や知識欲をかきたてる余白がありません。現在、提供される娯楽や創作物の多くが、そんなわかりやすさに特化しているように感じます。
難しいことを難しいままに、わからないことをわからないままに投じてくる自然に触れる体験。もしくは受け手に寄り添いつつも想像の余白を残してくれるような、そんな表現に触れる体験が、大人にも子どもにも必要だと思います。
本書はセンス・オブ・ワンダーを呼び起こして、今すぐ外に飛び出したくなるような気持ちにさせてくれる名著でした。5年後も10年後も、たぶん、折に触れて読み返す本。








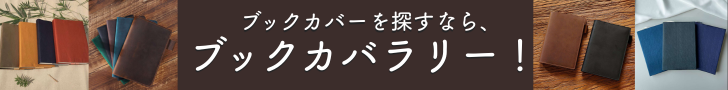


コメント